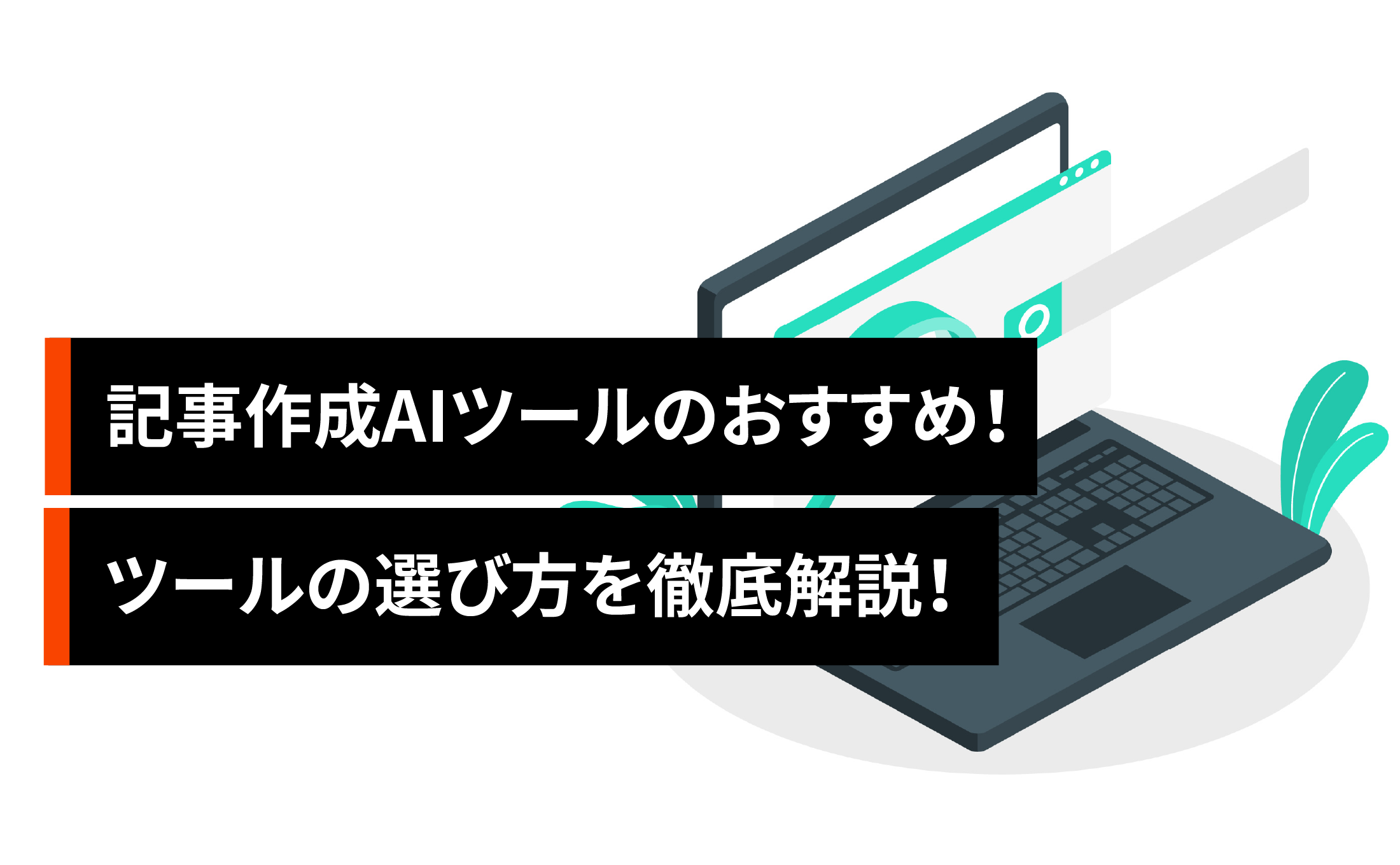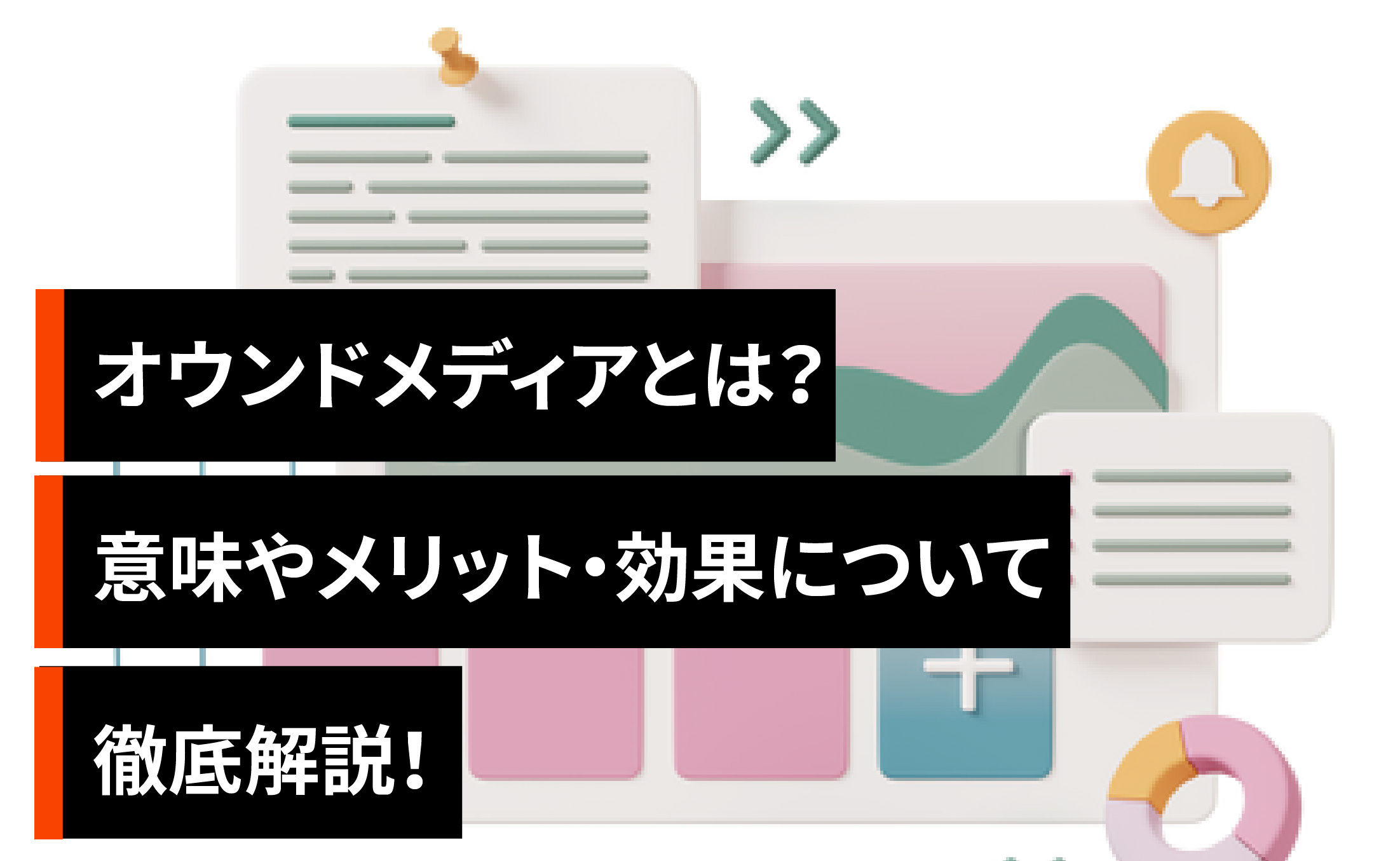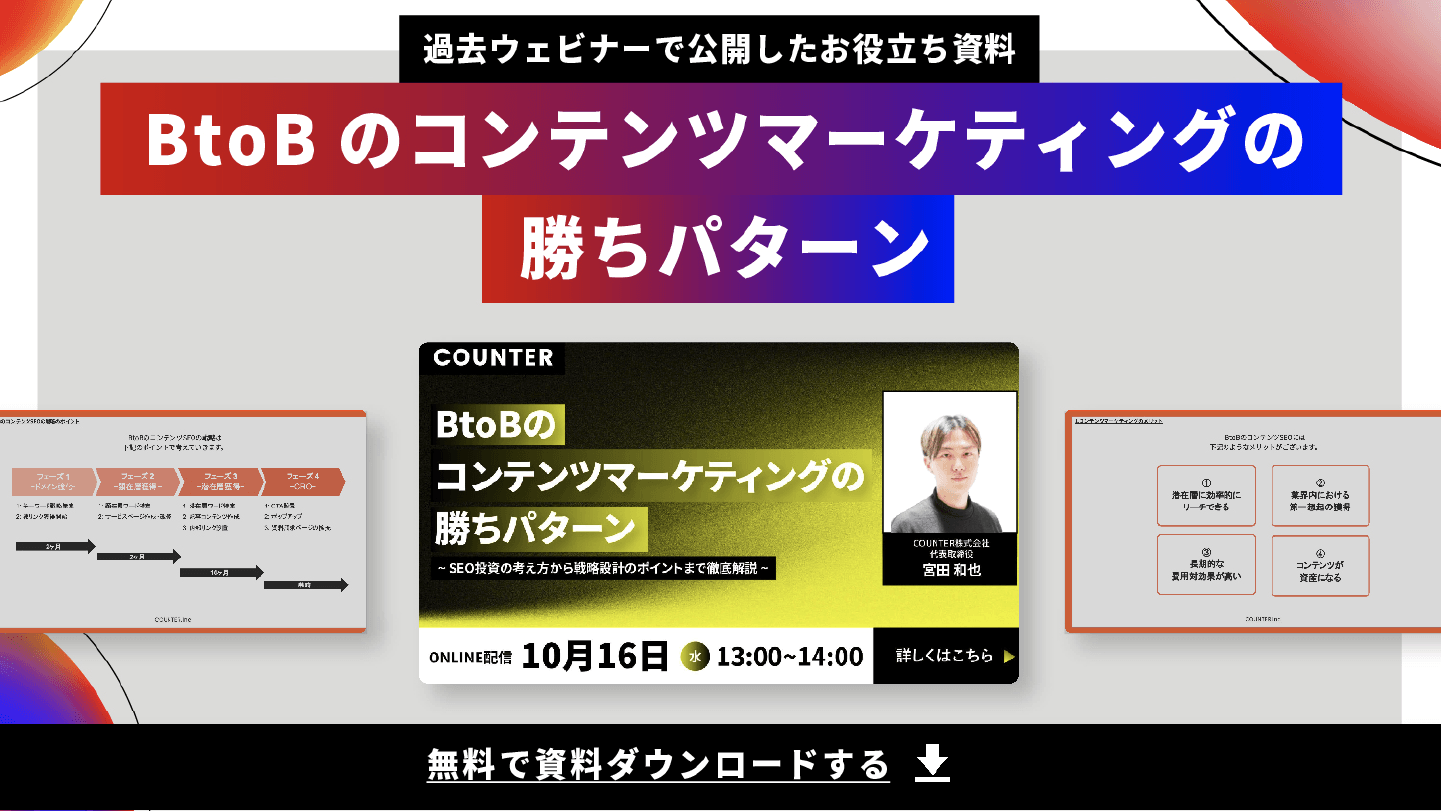Service Contents
コンテンツマーケティングのフレームワーク12選!カテゴリーごとに紹介!
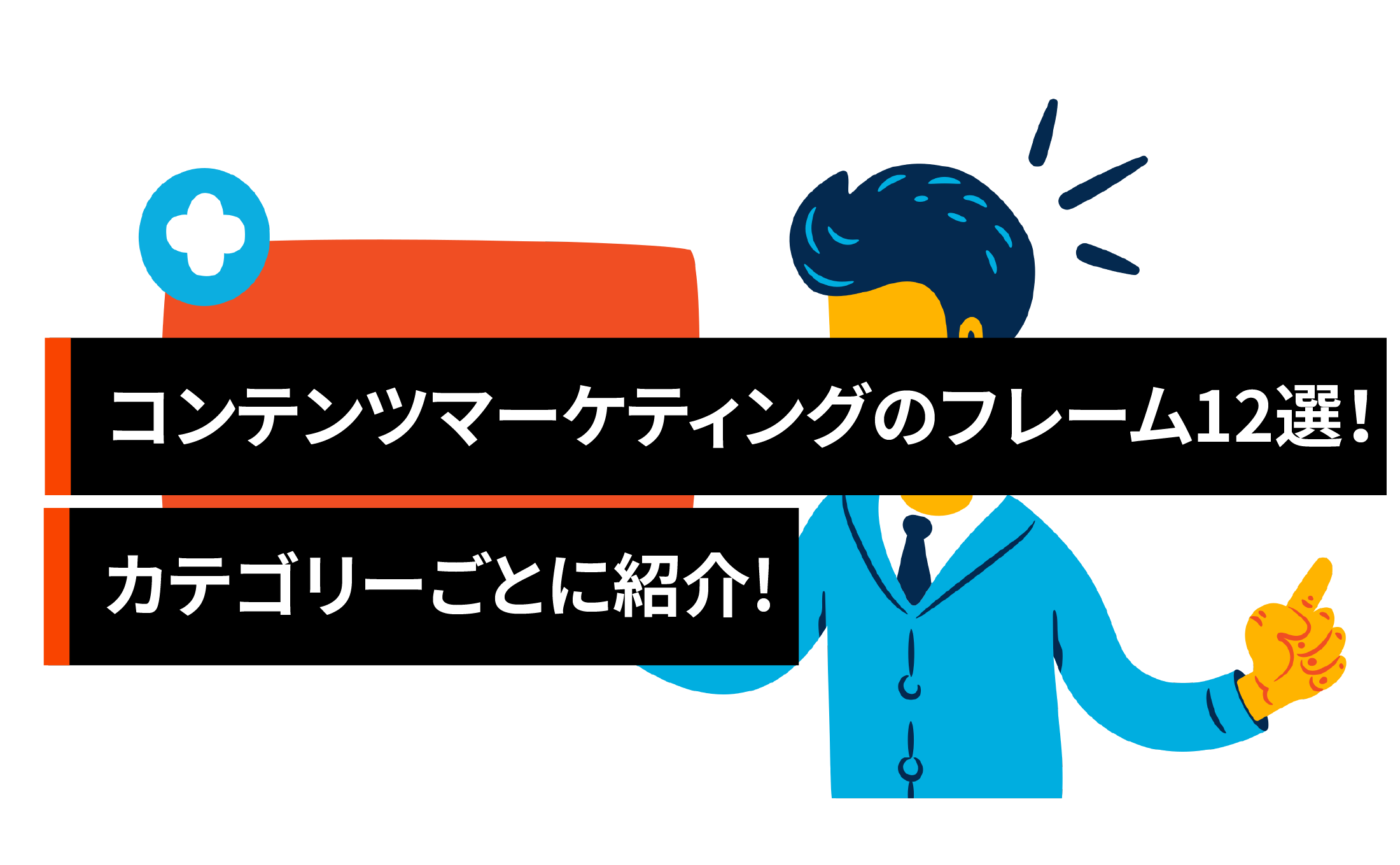
コンテンツを発信しているのに成果につながらない、改善の方向性が見えないと感じることも多いのではないでしょうか。
本記事では、コンテンツマーケティングを戦略的に進めるためのフレームワークを紹介します。
本記事で解説する内容
① 市場分析に活用できるフレームワーク
② 企画立案を助けるフレームワーク
③ 目標設定や改善に使えるフレームワーク
各フレームワークの役割と使い方を理解することで、マーケティング施策に一貫性が生まれます。戦略的にコンテンツマーケティングを進めたい方に向けて、基礎から応用まで役立つフレームワークをわかりやすくご紹介していきます。

X(旧: Twitter): @webkirin
COUNTER株式会社 代表取締役/SEOコンサルタント。
1993年生まれ。大学卒業後に外資系ITコンサルティング企業にてERP導入コンサルタントとして複数のシステム運用プロジェクトを経験。その後、CINCにてWebアナリスト、株式会社バンケッツにて不動産メディア事業責任者を経験し独立。フリーランスSEOコンサルタントを経験した後にニュートラルワークスにジョイン。SEO/コンテンツマーケティング戦略を得意分野とする。
◆ 経歴
2017年 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社/システムエンジニア(SAP Basis)
2018年 キャップジェミニ株式会社/ITコンサルタント(SAP SD/MM)
2019年 株式会社CINC/Webマーケティングアナリスト
2019年 株式会社バンケッツ/事業責任者(不動産メディア事業)
2020年 独立/Webマーケティングコンサルタント
2022年 株式会社ニュートラルワークス/執行役員 SEOコンサルティングリード
2024年 COUNTER株式会社 代表取締役
◆ 得意領域
・SEO戦略策定から実装支援(データベース・コンテンツ)
・コンテンツマーケティング戦略策定から実装支援
市場分析で使えるコンテンツマーケティングのフレームワーク5つ

コンテンツマーケティングを成功させるためには、まず市場を正確に分析することが重要です。市場分析は、ターゲットオーディエンスの理解や競合状況の把握に役立ち、効果的な戦略を立てる基盤となります。
市場分析で使えるコンテンツマーケティングのフレームワーク5つ
① STP分析
② 3C分析
③ 5フォース分析
④ SWOT分析
⑤ PEST分析
特に有用な5つのフレームワークを紹介します。
STP分析
STP分析は、マーケティング戦略を構築する上で重要なフレームワークです。STPは「Segmentation(セグメンテーション)」「Targeting(ターゲティング)」「Positioning(ポジショニング)」の頭文字を取ったもので、より効果的なコンテンツマーケティングを実現します。
まず、セグメンテーションでは市場を細分化し、異なるニーズや特性を持つ顧客グループを特定します。これにより、どのセグメントに対してアプローチするかを明確にすることが可能です。
次に、ターゲティングでは、特定したセグメントの中から最も魅力的なターゲットを選定します。ターゲットの購買力や市場の競争状況を考慮し、リソースを最も効果的に配分するための判断が重要です。
最後に、ポジショニングでは選定したターゲットに対して自社の製品やサービスがどのように認識されるべきかを定義します。競合との差別化を図り、顧客にとっての価値を明確にすることで、ブランドの強化につながります。
STP分析を活用することで、マーケティング活動がより戦略的になり、顧客のニーズに応じたコンテンツを提供することが可能です。コンテンツマーケティングの効果を最大化し、持続的な成長を促進することができるのです。
3C分析
3C分析は、コンテンツマーケティングにおいて重要なフレームワークであり、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの要素を中心に市場を分析します。
まず、顧客(Customer)については、ターゲットとなる顧客層のニーズや行動パターンを深く理解することが大切です。顧客のペルソナを明確にし、どのようなコンテンツが彼らに響くのかを考えるようにしていきましょう。
次に、同じ市場で競争している他社の強みや弱みを把握し、自社のポジショニングを明確にする競合(Competitor)分析です。競合のコンテンツ戦略やマーケティング手法を分析することで、自社の差別化ポイントを見つけ出すことができます。
最後に、自社(Company)の分析では、自社のリソースや能力を評価し、どのようなコンテンツを提供できるのかを考えます。自社の強みを活かしたコンテンツを作成することで、競争優位性を確立することができます。
5フォース分析
5フォース分析は、業界の競争環境を理解するための強力なフレームワークです。具体的には、業界内の競争、潜在的な新規参入者の脅威、代替品の脅威、顧客の交渉力、そして供給者の交渉力の5つの要素です。
まず、業界内の競争は、同業他社との競争の激しさを示します。競争が激しい場合、価格競争やサービスの差別化が求められ、企業は独自の価値を提供する必要があります。
次に、新規参入者の脅威は参入障壁の高さによって変わります。参入障壁が低い業界では、新たな競合が現れやすく、既存企業は常に警戒が必要です。
代替品の脅威は、顧客が他の製品やサービスに乗り換える可能性を示します。代替品が多い場合、企業は自社の製品の魅力を高める努力が求められます。
最後に、供給者の交渉力は原材料やサービスを提供する側の影響力です。供給者が少ない場合、企業は価格や条件に対して弱い立場に置かれることがあります。
5フォース分析を活用することで、企業は自社の立ち位置を明確にし、競争戦略を立てる際の重要な指針を得ることができます。
SWOT分析
SWOT分析は、企業やプロジェクトの現状を把握し、戦略を立てるための強力なフレームワークです。内部環境と外部環境を評価することで、組織の強み(Strengths)や弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を明確にします。
まず、強みと弱みの分析では、自社のコンテンツの質やブランド力、リソースの充実度などを評価します。競合他社に対してどのような優位性があるのか、または改善が必要な点は何かの把握が可能です。
次に、機会と脅威の分析では、市場のトレンドや競合の動向、消費者のニーズの変化など外部要因を考慮します。これにより、今後の戦略においてどのようなチャンスを活かすべきか、またはリスクを回避するためにどのような対策が必要かを見極められます。
SWOT分析を行うことで、コンテンツマーケティングの戦略をより具体的に策定でき、効果的な施策を打ち出すための基盤を築くことが可能です。特に、競争が激しい市場においては、自社の強みを最大限に活かし、弱みを克服するための戦略が重要と言えるでしょう。
PEST分析
PEST分析は、外部環境を評価するためのフレームワークで、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの要因を考慮します。企業が市場における機会や脅威を特定し、戦略を立てる際に有効です。
まず、政治的要因では政府の政策や規制、税制の変化などが企業活動に与える影響を評価します。例えば、新しい法律の施行や貿易政策の変更が、特定の業界にどのように影響するかを考えることが重要です。
次に、経済的要因では経済成長率、失業率、インフレ率などのマクロ経済指標が企業の業績に与える影響を分析します。これにより、消費者の購買力や市場の需要を予測することができます。
社会的要因は、消費者のライフスタイルや価値観、人口動態の変化を考慮する内容です。ターゲット市場のニーズや嗜好を理解し、より効果的なコンテンツを企画するための基盤を築くことが可能です。
最後に、技術的要因では、技術革新や新しいテクノロジーの登場が市場に与える影響を評価します。特にデジタルマーケティングの進化は、コンテンツの配信方法や消費者とのインタラクションに大きな変化をもたらしています。
PEST分析を通じて、企業は外部環境を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報を得る機会となるでしょう。
コンテンツの企画出しで用いるマーケティングフレームワーク3つ

コンテンツマーケティングにおいて、効果的な企画を立てるためには、適切なフレームワークを活用することが重要です。
コンテンツの企画出しで用いるマーケティングフレームワーク3つ
① コンテンツファネル分析
② PASONAの法則
③ 4P分析
特に役立つ3つのフレームワークを紹介します。
コンテンツファネル分析
コンテンツファネル分析は、顧客の購買プロセスを理解し、各ステージにおけるコンテンツの役割を明確にするためのフレームワークです。潜在顧客が認知から購入、さらにはリピート購入に至るまでの過程を可視化し、どの段階でどのようなコンテンツが必要かを示します。
ファネルは通常、認知、興味、評価、購入、リピートの5つのステージに分かれています。最初の認知段階では、ブログ記事やSNS投稿などの情報提供型コンテンツが効果的です。
次に興味を引くためには、ウェビナーやホワイトペーパーなど、より深い情報を提供するコンテンツが求められます。評価段階では、製品の比較やレビュー、ケーススタディなど、具体的な情報を提供することが重要です。
購入段階では、特別オファーやクーポンなど、顧客が行動を起こすためのインセンティブを用意することが効果的です。そして、リピート購入を促すためには、顧客へのフォローアップや、関連商品を提案するコンテンツが役立ちます。
コンテンツファネル分析を活用することで、各ステージにおける顧客のニーズを的確に把握し、それに応じたコンテンツを提供することが可能になります。
関連記事: コンテンツマーケティングとは?メリットや始め方・成功事例と企業戦略をわかりやすく解説
PASONAの法則
PASONAの法則は、効果的なコンテンツ企画を支えるためのフレームワークとして広く利用されています。PASONAの法則は、Problem(問題)、Affinity(親近感)、Solution(解決策)、Offer(提案)、Narrowing down(絞り込み)、Action(行動)の6つの要素から成り立っています。
まず、Problemでは、顧客が抱える具体的な問題を明確にします。次に、Affinityでは、問題に対する共感を示し、顧客との信頼関係を築くことが重要です。Solutionでは、顧客の問題を解決するための具体的な提案を行い、Offerではその提案を魅力的に提示します。
Narrowing downでは、ターゲットを絞り込み、最も関心を持つ層にアプローチし、そして最後に、Actionでは、顧客に対して具体的な行動を促すことが大切なポイントです。
PASONAの法則を活用することで、コンテンツが単なる情報提供に留まらず、顧客の心に響くストーリーを展開することができます。結果として、より高いエンゲージメントを得ることができ、コンテンツマーケティングの効果を最大化することが期待できるでしょう。
4P分析
4P分析は、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素から成り立っています。
まず、製品(Product)については、顧客のニーズや期待に応える内容を考えることが重要です。どのような価値を提供できるのか、競合と差別化するポイントは何かを明確にすることで、魅力的なコンテンツを生み出す基盤が整います。
次に、価格(Price)は、提供するコンテンツの価値に見合った適切な価格設定を行うことが重要です。無料コンテンツと有料コンテンツのバランスを考え、顧客が納得できる価格を設定することで、より多くのユーザーを引きつけることができます。
流通(Place)は、コンテンツがどのように顧客に届けられるかを考える要素です。オンラインプラットフォームやSNSなど、ターゲット層が集まる場所でコンテンツを配信することで、より多くの人々にリーチすることが可能になります。
最後に、プロモーション(Promotion)は、コンテンツを効果的に広めるための戦略です。広告やSNSでのシェア、インフルエンサーとのコラボレーションなど、多様な手法を駆使してコンテンツの認知度を高めることが重要です。
4P分析を活用することで、コンテンツマーケティングの戦略をより具体的かつ効果的に構築でき、結果として目標達成に近づくことができるでしょう。
コンテンツマーケティングの目標達成に役立つフレームワーク4つ

コンテンツマーケティングにおいて、目標達成は成功の鍵となります。そのためには、適切なフレームワークを活用することが重要です。
コンテンツマーケティングの目標達成に役立つフレームワーク4つ
① KPIツリー
② SMARTゴール
③ RFM分析
④ デシル分析
目標管理を強化するための4つのフレームワークを紹介します。
KPIツリー
KPIツリーは、企業やプロジェクトの目標を達成するために必要な重要業績評価指標(KPI)を階層的に整理したフレームワークです。全体の目標から具体的な行動指標までを明確にし、各指標がどのように相互に関連しているかを視覚的に把握することができます。
KPIツリーは、まず最上位に企業全体の目標を設定し、その下に各部門やプロジェクトの目標を配置します。さらに、それぞれの目標に対して具体的なKPIを設定し、進捗を測定するための基準を明確にしていきましょう。
例えば、企業の売上向上を最上位の目標とした場合、その下にマーケティング部門のリード獲得数や営業部門の成約率などの具体的なKPIを設定します。これにより、各部門がどのように貢献できるかを明確にし、全体の戦略に対する理解を深めることが可能です。
KPIツリーは、定期的に見直しを行うことで、変化する市場環境やビジネスニーズに柔軟に対応できる点も魅力です。コンテンツマーケティングにおいても、KPIツリーを活用することで、効果的な施策を立案し、成果を最大化するための強力なツールとなるでしょう。
SMARTゴール
SMARTゴールは目標を「Specific(具体的)」「Measurable(測定可能)」「Achievable(達成可能)」「Relevant(関連性がある)」「Time-bound(期限がある)」の5つの要素に分けて考えることを促します。
まず、具体的な目標を設定することが重要です。例えば、「ウェブサイトの訪問者数を増やす」という漠然とした目標ではなく、「次の四半期までに訪問者数を20%増加させる」といった具体的な数値を設定することで、チーム全体が同じ方向に向かいやすくなります。
次に、測定可能な指標を設定することが大切です。目標達成の進捗を確認するためには、数値で評価できる指標が必要です。例えば、コンテンツのエンゲージメント率やリード獲得数など、具体的なデータをもとに進捗を追跡します。
また、達成可能な目標を設定することも重要です。現実的な範囲内での目標を設定することで、チームのモチベーションを維持しやすくなります。過度に高い目標は、逆に士気を下げる原因となることがあるので注意しましょう。
さらに、関連性のある目標を設定することも忘れてはいけません。ビジネス全体の戦略や目的に沿った目標を設定することで、コンテンツマーケティングの活動がより効果的になります。
最後に、期限を設けることが重要です。目標には明確な期限を設定することで、チームがその目標に向かって集中しやすくなります。例えば、「次のキャンペーンまでにリード数を増やす」といった具体的な期限を設けることで、行動計画が立てやすくなります。
RFM分析
RFM分析は「Recency(最近の購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(購入金額)」の頭文字を取ったものです。
まず、Recencyは顧客が最後に購入した日からの経過時間のことです。最近購入した顧客は、再度購入する可能性が高いため、特別なプロモーションやフォローアップを行うことで、リピート率を向上させられます。
次に、Frequencyは顧客が一定期間内に何回購入したかを示します。頻繁に購入する顧客は、ブランドへのロイヤルティが高いと考えられ、特別なオファーやロイヤルティプログラムを提供することで、さらなる関係構築が期待できます。
最後に、Monetaryは顧客が過去にどれだけの金額を使ったかです。高額な購入を行った顧客は、価値のある顧客と見なされ、高級な商品やサービスを提案することで、さらなる売上を見込むことができます。
RFM分析を活用することで、企業は顧客の行動を深く理解し、効果的なマーケティング施策を展開することが可能です。顧客のニーズに応じたパーソナライズされたアプローチが可能となり、コンテンツマーケティングの目標達成に大きく寄与すると言えるでしょう。
デシル分析
デシル分析は、顧客を10のグループに分けて、その購買行動や価値を評価する手法です。具体的には、顧客を購入金額や頻度に基づいてランク付けし、上位の顧客(上位10%)が全体の売上にどれほど寄与しているかを把握します。
デシル分析を行うことで、企業はどの顧客層が最も価値が高いのかを明確にし、その層に対するマーケティング戦略を強化することが可能です。
また、デシル分析は、顧客の流出を防ぐための施策を考える際にも有効です。低いランクの顧客に対しては、再度関心を引くためのアプローチを検討することで、全体の顧客基盤を強化することができます。
デシル分析はコンテンツマーケティングにおいても、ターゲットを明確にし、効果的な施策を打つための重要なフレームワークとなります。
まとめ
コンテンツマーケティングは、戦略的なアプローチが求められる分野です。本記事では、市場分析、コンテンツ企画、目標管理に役立つフレームワークをそれぞれ紹介しました。
紹介したフレームワークを駆使することで、コンテンツマーケティングの全体像が明確になり、より効率的に目標達成へと近づくことができるでしょう。ぜひ、これらの知識を活用し、マーケティング活動を一層充実させてください。