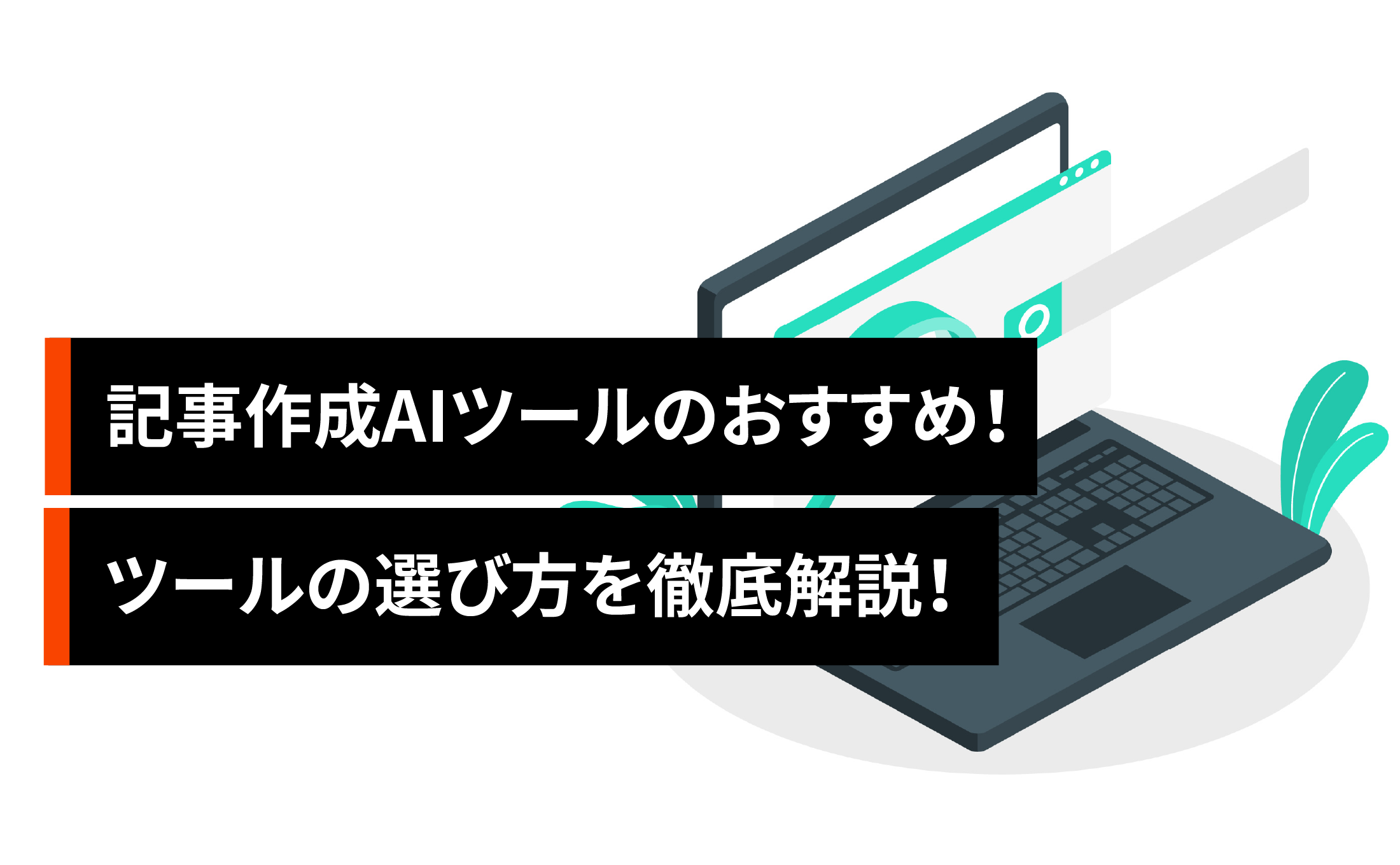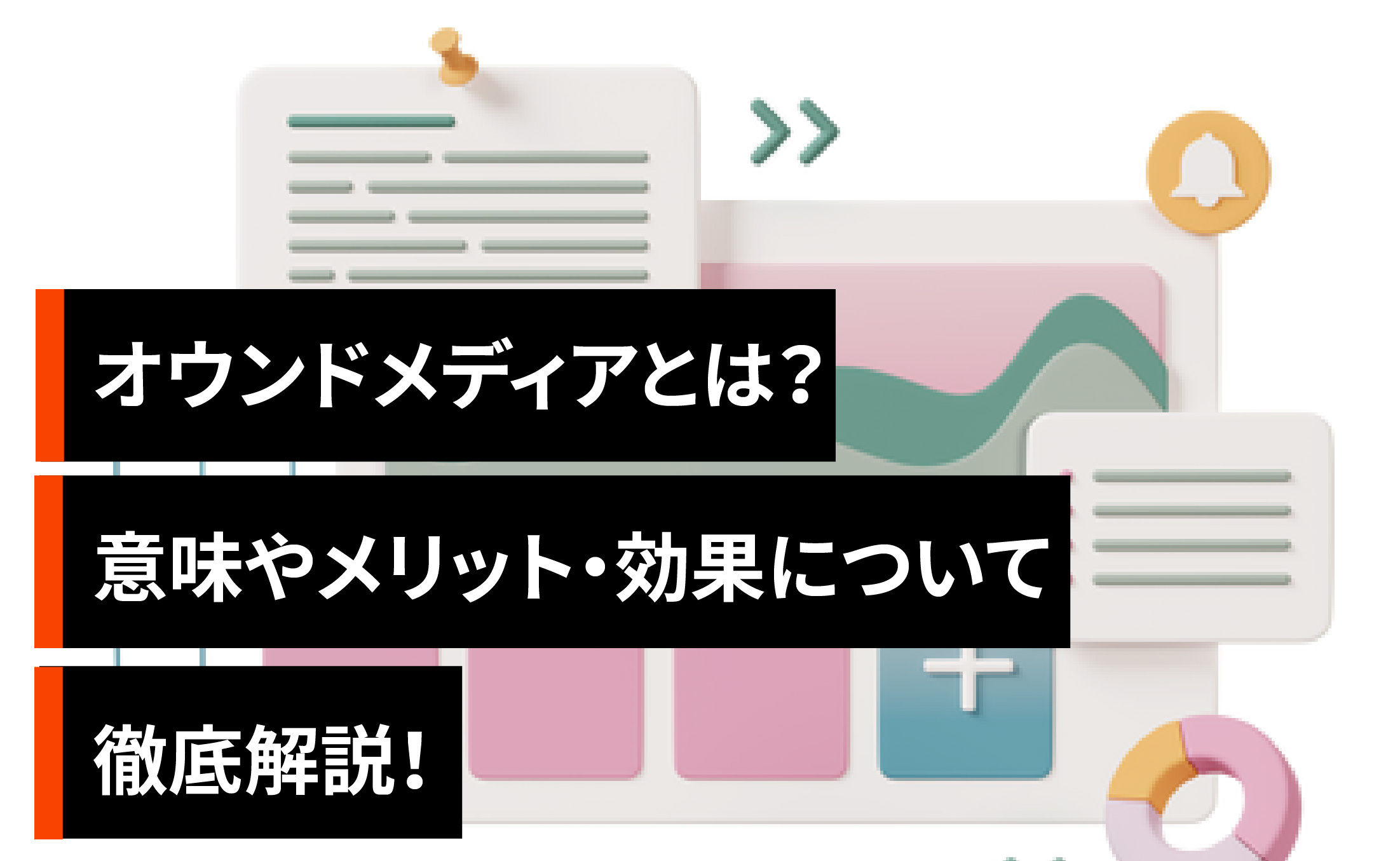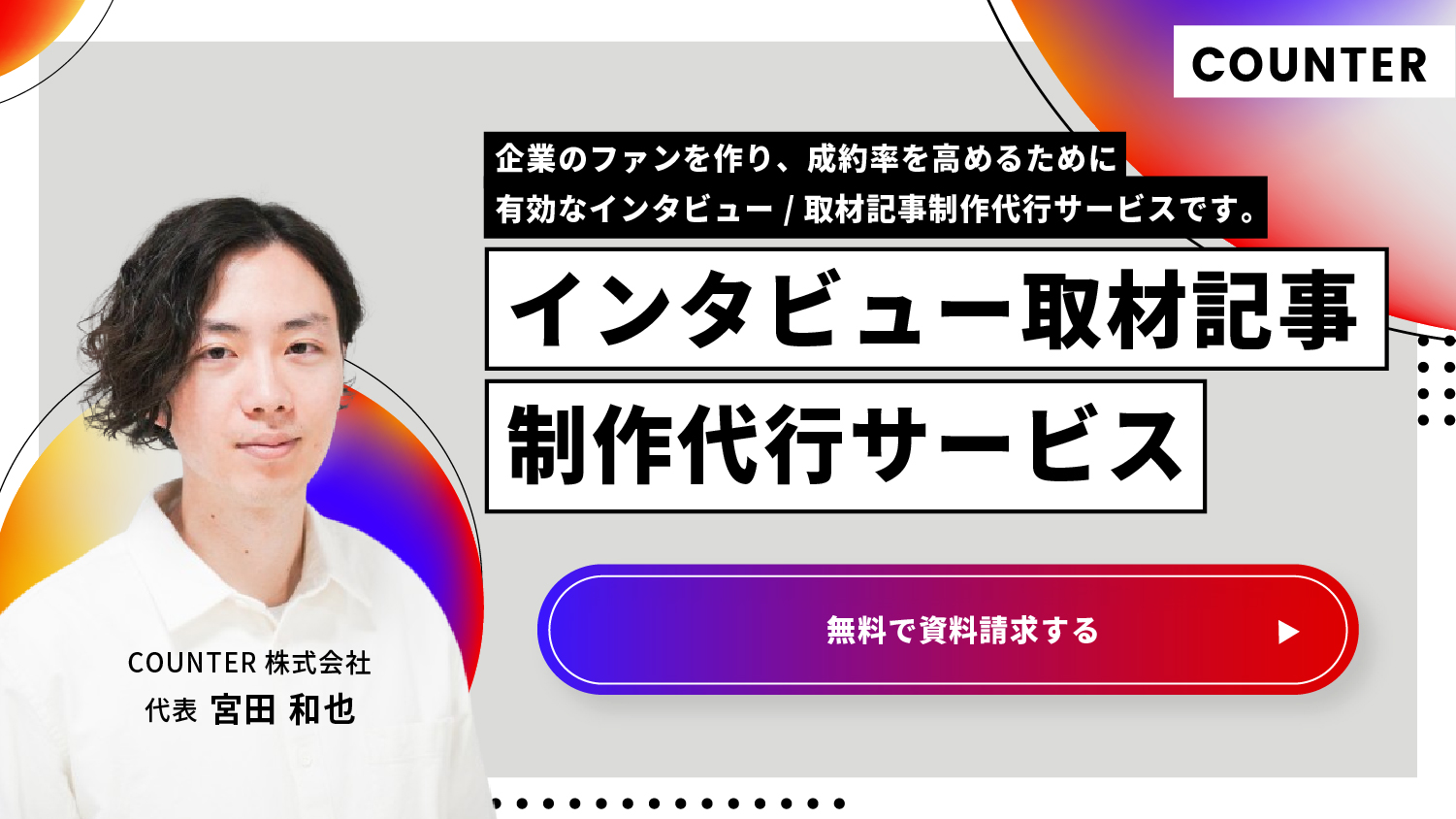Service Contents
インタビュー記事の著作権は誰にある?正しい取り扱いと違法の線引き
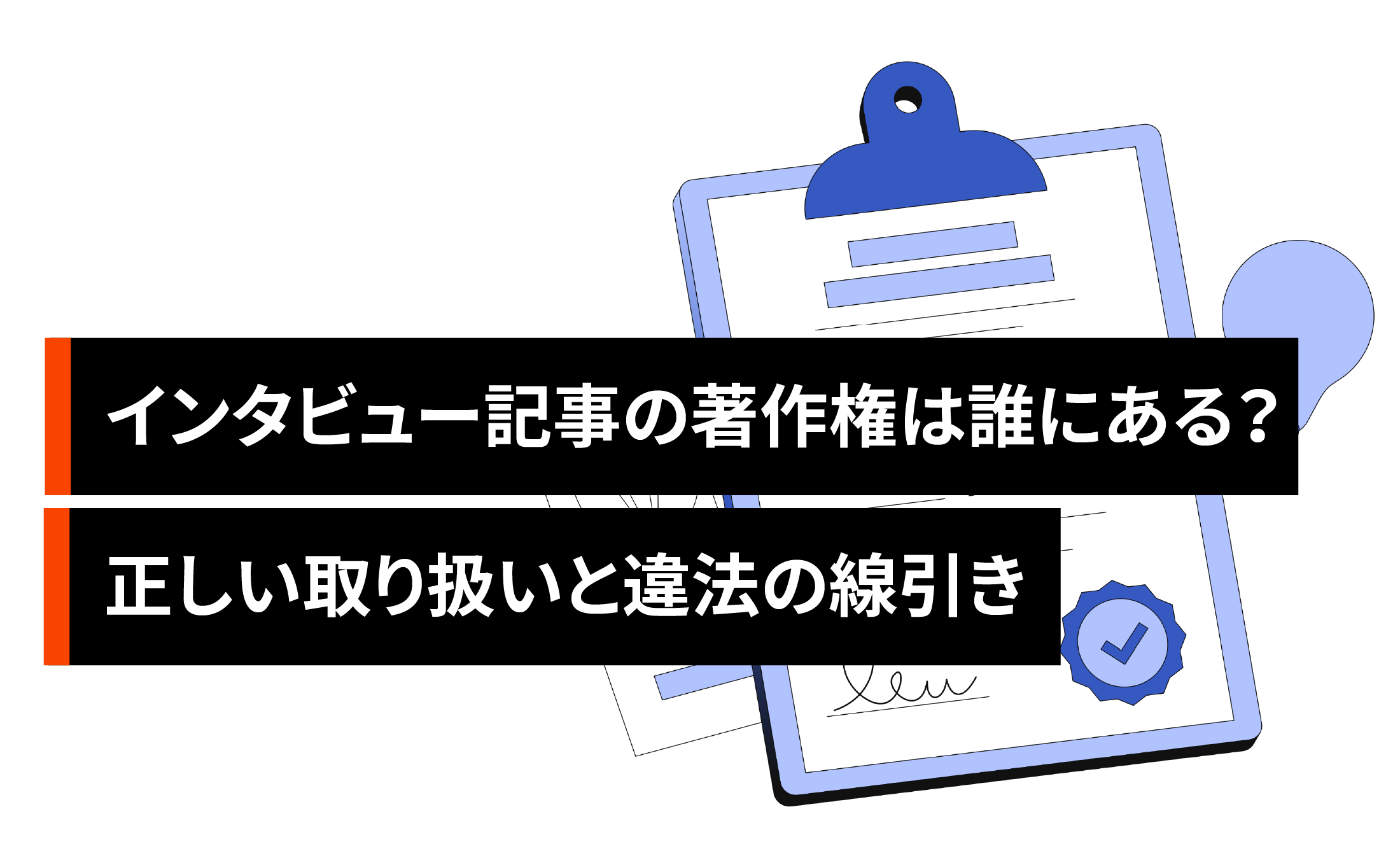
インタビュー記事の著作権は、通常はその制作過程に関わった人物や団体に帰属します。ただし、厳密には、誰に権利があるかは状況や契約内容によって異なります。
場合によっては共同著作物として両者に著作権が帰属することもあるでしょう。
本記事で解説する内容
① インタビュー記事の著作権は誰にあるのか
② 著作権法を犯しているインタビュー記事の例
③ インタビュー記事の引用の仕方
本記事を読むことで、インタビュー記事の扱い方や権利の守り方など、著作権についての理解を深めてトラブルを回避できるようになります。

X(旧: Twitter): @webkirin
COUNTER株式会社 代表取締役/SEOコンサルタント。
1993年生まれ。大学卒業後に外資系ITコンサルティング企業にてERP導入コンサルタントとして複数のシステム運用プロジェクトを経験。その後、CINCにてWebアナリスト、株式会社バンケッツにて不動産メディア事業責任者を経験し独立。フリーランスSEOコンサルタントを経験した後にニュートラルワークスにジョイン。SEO/コンテンツマーケティング戦略を得意分野とする。
◆ 経歴
2017年 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社/システムエンジニア(SAP Basis)
2018年 キャップジェミニ株式会社/ITコンサルタント(SAP SD/MM)
2019年 株式会社CINC/Webマーケティングアナリスト
2019年 株式会社バンケッツ/事業責任者(不動産メディア事業)
2020年 独立/Webマーケティングコンサルタント
2022年 株式会社ニュートラルワークス/執行役員 SEOコンサルティングリード
2024年 COUNTER株式会社 代表取締役
◆ 得意領域
・SEO戦略策定から実装支援(データベース・コンテンツ)
・コンテンツマーケティング戦略策定から実装支援
インタビュー記事の著作権は誰にあるのか

インタビュー記事の著作権は、インタビューを実施した側と受けた側のどちらに帰属するかが重要なポイントです。しかし、インタビュー対象者が提供する情報や発言が記事の核心をなす場合、彼らにも著作権が認められることがあります。
このように、著作権の帰属は一概には決まらず、具体的な契約内容や合意によって異なるため、事前に明確にしておくことが重要です。
インタビュー記事の著作権の帰属先
① インタビューした側にある場合
② インタビューを受けた側にある場合
③ 共同著作物になる場合
著作権に関する3つのパターンを解説していきます。
インタビューした側にある場合
インタビュー記事の著作権がインタビュアーに帰属するのは、制作過程における創造性や労力が評価されるためです。質問の構成、進行、執筆の中で、独自の視点や表現が加えられることが多く、著作物として認められる場合があります。
特に、内容の取捨選択や文章表現に工夫を加えた場合、創作性が発揮されたと判断されやすくなります。
ただし、記事の大部分がインタビュー対象者の発言に依拠している場合は注意が必要です。著作権の帰属は、編集や表現にどれだけ創造性が加わっているかによって左右されます。
そのため、取材を行う前に、著作権に関する合意を明確にしておくことが重要です。したがって、インタビューを行う際には、事前に著作権についての合意を明確にしておきましょう。これにより、後々のトラブルを避けることができ、双方の権利を守ることができます。
インタビューを受けた側にある場合
インタビュー記事の著作権がインタビュー対象者に帰属するケースもあります。これは、発言が個人的見解や創造的な表現を含む場合や、対象者が特定の目的で内容を使用したいと希望している場合に見られます。
たとえば、自伝や専門書、講演などで自らの発言を活用したいときには、著作権を持つことで自由な利用が可能です。特に著名人や専門家の発言には独自性があるため、対象者に権利が認められることも少なくありません。
ただし、著作権の帰属は契約内容によって左右されるため、インタビューを行う際には、事前に明確な合意を交わすことが重要です。このように、インタビューを受けた側に著作権がある場合は、その内容の利用においても慎重な取り扱いが求められます。
共同著作物になる場合
インタビュー記事が共同著作物と見なされる場合、著作権はインタビュアーとインタビュー対象者の双方に帰属します。これは、質問を通じて内容を構成する側と、回答によって情報を提供する側が共に作品の完成に貢献しているためです。
両者の役割が不可分な関係にあると判断されるケースでは、共同著作物としての扱いが適用されます。この場合、記事を利用する際には、基本的に両者の同意が必要です。
ただし、著作権の管理や使用条件については、事前に契約を結んで整理しておくとよいでしょう。一方の権利を明確にすることも契約次第で可能なため、取材の段階で取り決めておくと安心です。円滑な制作とトラブル防止のためにも、著作権の扱いについて事前の確認を徹底しましょう。
インタビュー記事に使われている写真の著作権は誰か

インタビュー記事に使用される写真の著作権についても、著作権法の観点から重要なポイントが3つあります。
インタビュー記事に使われている写真の著作権の帰属先
① インタビュアーが撮影した写真
② インタビュー対象者が提供した写真
③ 第三者が撮影した写真
写真の著作権は原則として「撮影者」に帰属します。インタビュアーが撮影した場合はインタビュアーに、対象者が提供した写真は対象者に、第三者が撮影した場合はその第三者に著作権があります。
第三者の写真を使う場合は、著作権侵害を防ぐために必ず使用許可が必要です。また、著作権の扱いは契約で明確に定めることも可能なため、必要に応じて契約で詳細を決めましょう。
このように、インタビュー記事に使われる写真の著作権は、撮影者や提供者の権利を尊重し、適切に取り扱うことが重要です。著作権に関する理解を深めることで、インタビュー記事全体のクオリティを高め、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
インタビューされた側はインタビュー記事を自由に使えるのか?
インタビュー記事の内容をインタビュー対象者が自由に使用できるかどうかは、著作権の観点から慎重に考える必要があります。一般的に、記事の著作権はインタビュアーやメディアに帰属するため、対象者が自由に再利用することはできません。
ただし、契約や合意によって、発言内容の使用範囲が明確に定められている場合があります。たとえば、SNSでの発言引用が許可されていることもあります。一方で、商業利用は制限されることもあるため注意が必要です。
また、公に発表された記事の内容を引用することは可能ですが、著作権法に則った正当な引用でなければ、著作権侵害となるおそれがあります。自身の発言であっても、記事の扱いについては事前の確認と許可取得が重要です。
著作権法を犯しているインタビュー記事の利用例
インタビュー記事の利用において、著作権法を犯すケースは少なくありません。特に3つの利用例には注意が必要です。
著作権法を犯しているインタビュー記事の利用例
① インタビューされた動画やテレビ番組を書き起こした引用
② インタビューされた番組や雑誌記事の画像を使う
③ インタビュアーの写真を勝手に引用する
それぞれ解説していきます。
インタビューされた動画やテレビ番組を書き起こした引用
インタビュー記事で動画やテレビ番組から引用する場合は、著作権に特に注意が必要です。映像や音声には著作権が多く含まれているため、無断で文字起こしや引用を行うと、著作権侵害にあたる可能性があります。
また、発言を編集して引用する際には、文脈や意図を歪めないよう注意が必要です。不正確な引用は、著作権だけでなく名誉毀損やプライバシー侵害にもつながる恐れがあります。
引用の際は必ず原文の意図を尊重し、必要に応じて権利者の許可を得ることが大切です。
インタビューされた番組や雑誌記事の画像を使う
インタビュー記事に関連する番組や雑誌の画像を使用する際は、著作権への配慮が不可欠です。これらの画像は制作会社や出版社が著作権を有しており、無断使用は著作権侵害となる可能性があります。
テレビ番組のキャプチャや雑誌の誌面を転載する場合は、事前に許可を得ることが重要です。また、画像使用時には著作権者の意向を尊重し、適切にクレジットを記載するとトラブル回避にもつながります。
著作権を守ることは、記事の信頼性向上にも貢献します。特にインタビュー対象者の紹介目的で画像を使いたい場合でも、出典元の使用条件を確認し、必要に応じて正式な手続きを踏むことが大切です。
インタビュアーの写真を勝手に引用する
インタビュー記事でインタビュアーの写真を無断で使用することは、著作権法に違反する可能性があります。インタビュアーが自身で撮影した写真や、他媒体から引用した画像には著作権が存在し、許可なく使用すれば法的トラブルに発展する恐れがあります。
特に本人が撮影した写真は明確に著作権がインタビュアーに帰属しており、出典を記載していても事前の許可なしに使用することは認められません。著作権を尊重し、必要な手続きを経ることは、トラブル回避だけでなく、インタビュアーとの信頼関係を維持するうえでも重要です。
インタビュー記事を引用してもセーフになりやすい範囲

インタビュー記事を引用する際には、著作権を侵害しないためのポイントを押さえておくことが重要です。
インタビュー記事を引用してもセーフになりやすい範囲
① 一部の文章のみを引用する
② 誰の発言かを明確にする
③ 相手も得をする内容と引用方法にする
それぞれ解説していきます。
一部の文章のみを引用する
インタビュー記事を引用する際には、一部の文章のみを使用することが著作権法において比較的安全な方法とされています。具体的には、引用する部分が全体の文脈において重要な情報を提供し、かつその引用が必要不可欠である場合に限ります。このような引用は、著作権者の権利を侵害することなく、情報の共有を促進する手段となります。
ただし、引用する際には2つ注意点があります。
- 引用部分は明確に区別されるようにすること
- 元の著作物との関連性を示すこと
たとえば、引用符を用いることで、どの部分が引用であるかを明示することが重要です。また、引用の目的が批評や研究、報道などである場合、著作権法における「公正な利用」の範囲内に収まる可能性が高まります。
さらに、引用する際には、出典を明記することが求められます。これにより、引用の正当性が高まり、著作権者との信頼関係を築くことにもつながります。
インタビュー記事を引用する際には、これらのポイントを押さえ、適切な方法で情報を活用することが大切です。
誰の発言かを明確にする
インタビュー記事を作成する際、発言の出所を明確にすることは非常に重要です。具体的には、発言を引用する際には、発言者の名前や肩書きを明記し、どのような文脈でその言葉が発せられたのかを説明することが求められます。
例えば、「〇〇氏は、インタビューの中で『〇〇の重要性について考えるべきだ』と述べました」といった形で、発言者の情報をしっかりと記載することで、読者に対しても発言の信憑性を高めることができます。
また、発言の内容が誤解されないように、文脈を補足することも大切です。
これにより、インタビュー記事がより信頼性のあるものとなり、著作権の観点からも適切な取り扱いがなされていることを示すことができます。
相手も得をする内容と引用方法にする
インタビュー記事を引用する際には、引用された側にも利益があるような内容や方法を心掛けることが重要です。例えば、インタビュー対象者が自身の意見や考えを広める機会を得られるようにすることで、相手にとってもプラスになる引用が可能です。
具体的には、インタビュー記事の引用を行う際に、以下の情報を明記します。
- 対象者の名前
- 肩書き
読者は誰の発言であるかを理解しやすくなり、対象者の認知度向上にも寄与します。また、引用する内容が対象者の専門性や経験に基づいている場合、その情報が他の読者にとっても価値あるものとなり、結果的に対象者の信頼性を高めることにもつながります。
さらに、引用の際には、インタビュー対象者に事前に確認を取ることも良い方法です。確認を取ることで、相手の意向を尊重し、誤解を避けることができます。このように、相手も得をする内容や方法で引用を行うことは、著作権を守るだけでなく、良好な関係を築くためにも非常に有効です。
まとめ
インタビュー記事の著作権については、インタビュアーとインタビュー対象者の双方に権利が帰属する可能性があります。著作権の取り扱いは、契約内容や制作過程によって異なるため、事前に明確な合意を持つことが重要です。
また、インタビュー記事に使用される写真や引用の扱いについても著作権法を遵守することが求められます。著作権を正しく理解し、適切に扱うことで、権利を守りつつ、インタビュー記事を有効に活用することができるでしょう。インタビューを行う際には、著作権に関する知識を深め、トラブルを避けるための準備をしておくことが大切です。