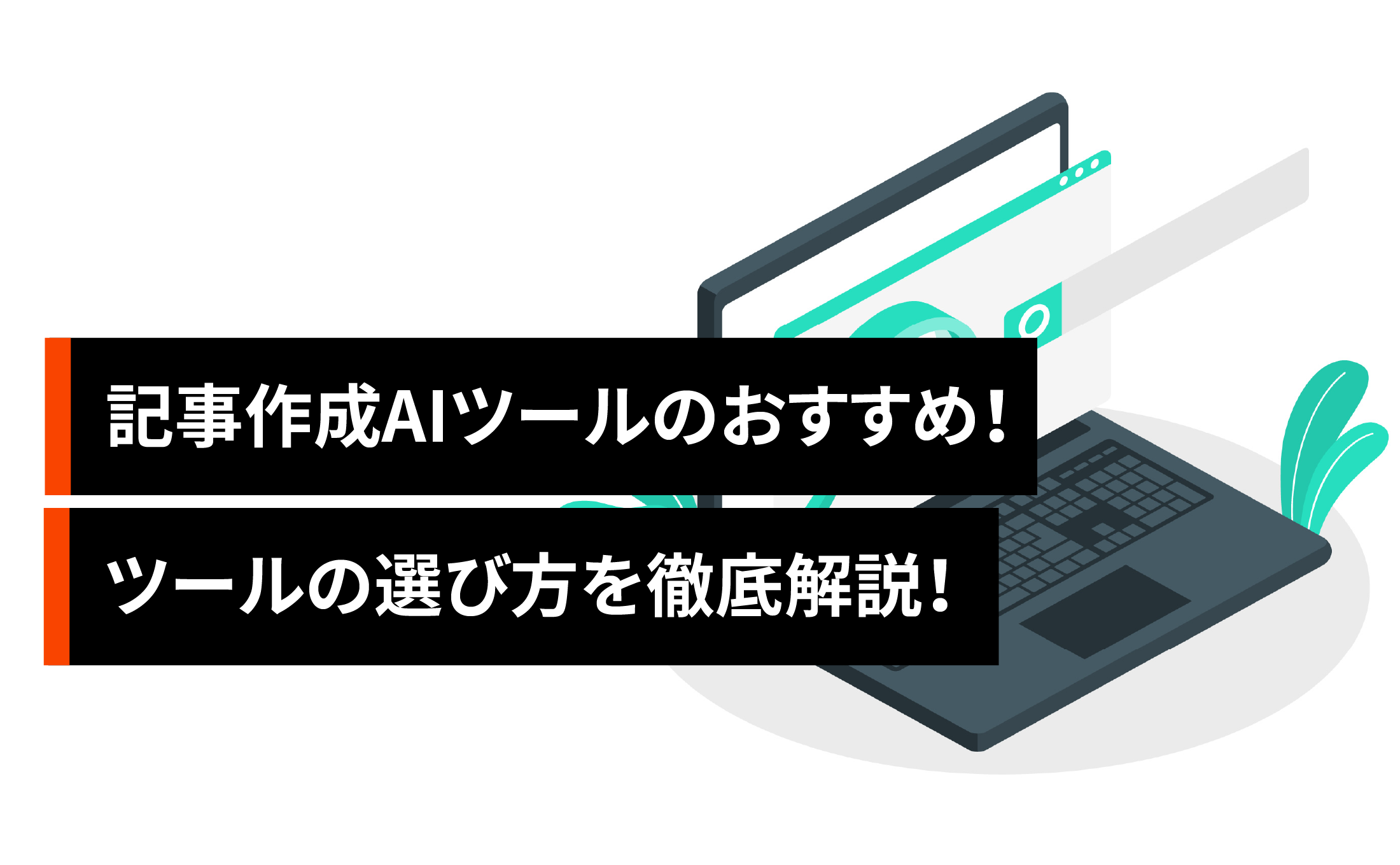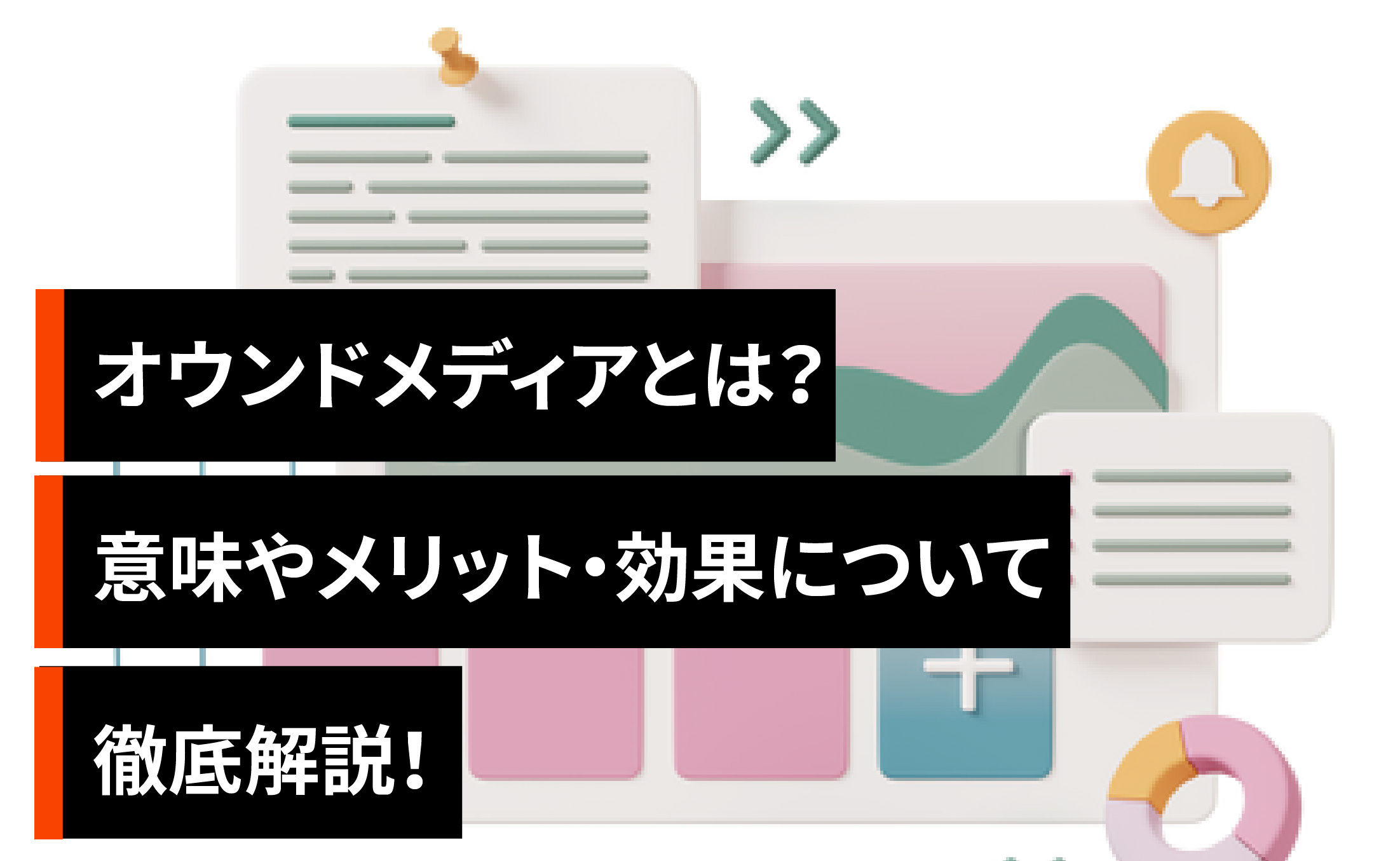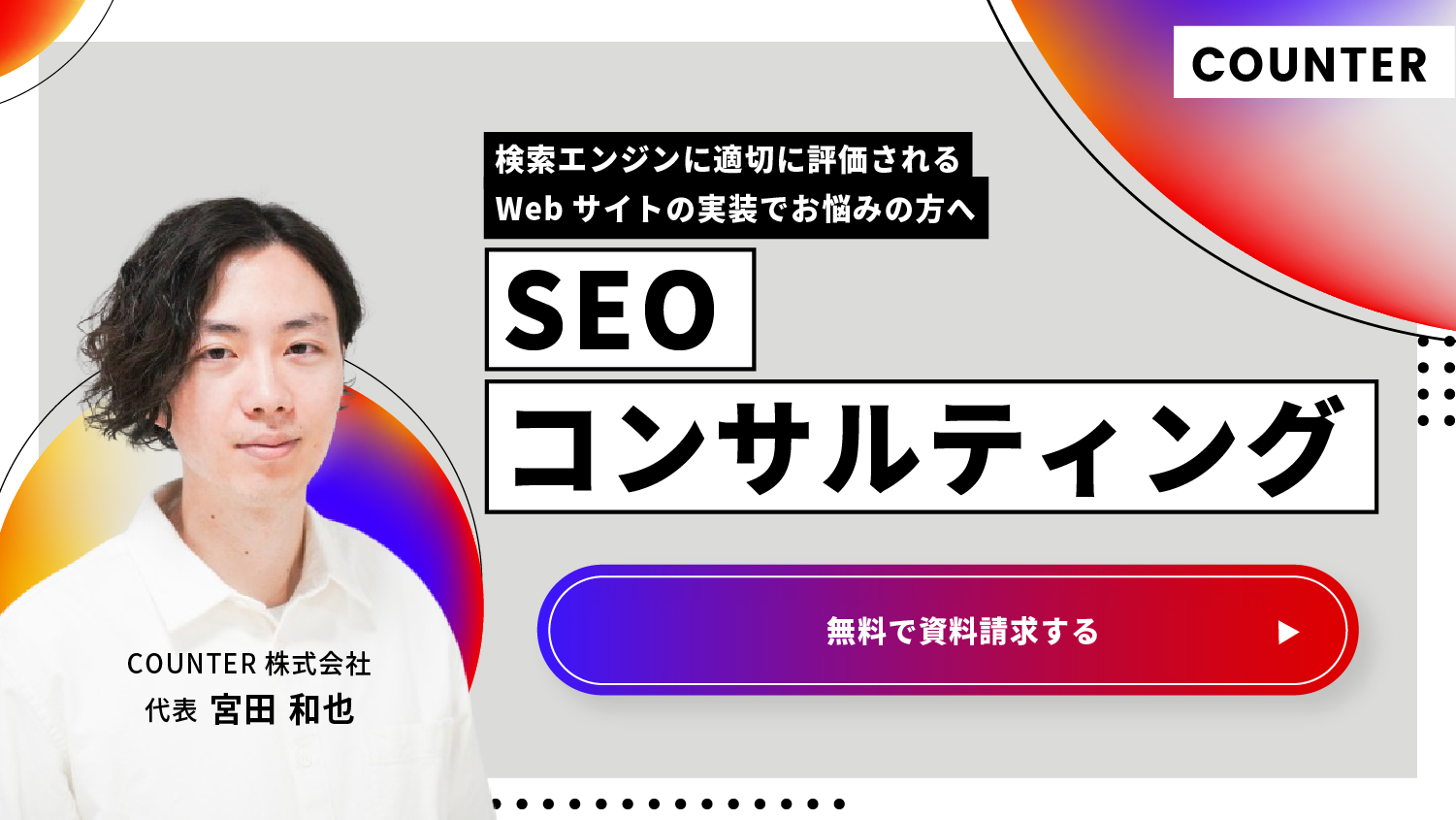Service Contents
SEOポイズニングとは?仕組みや対策、事例を紹介!
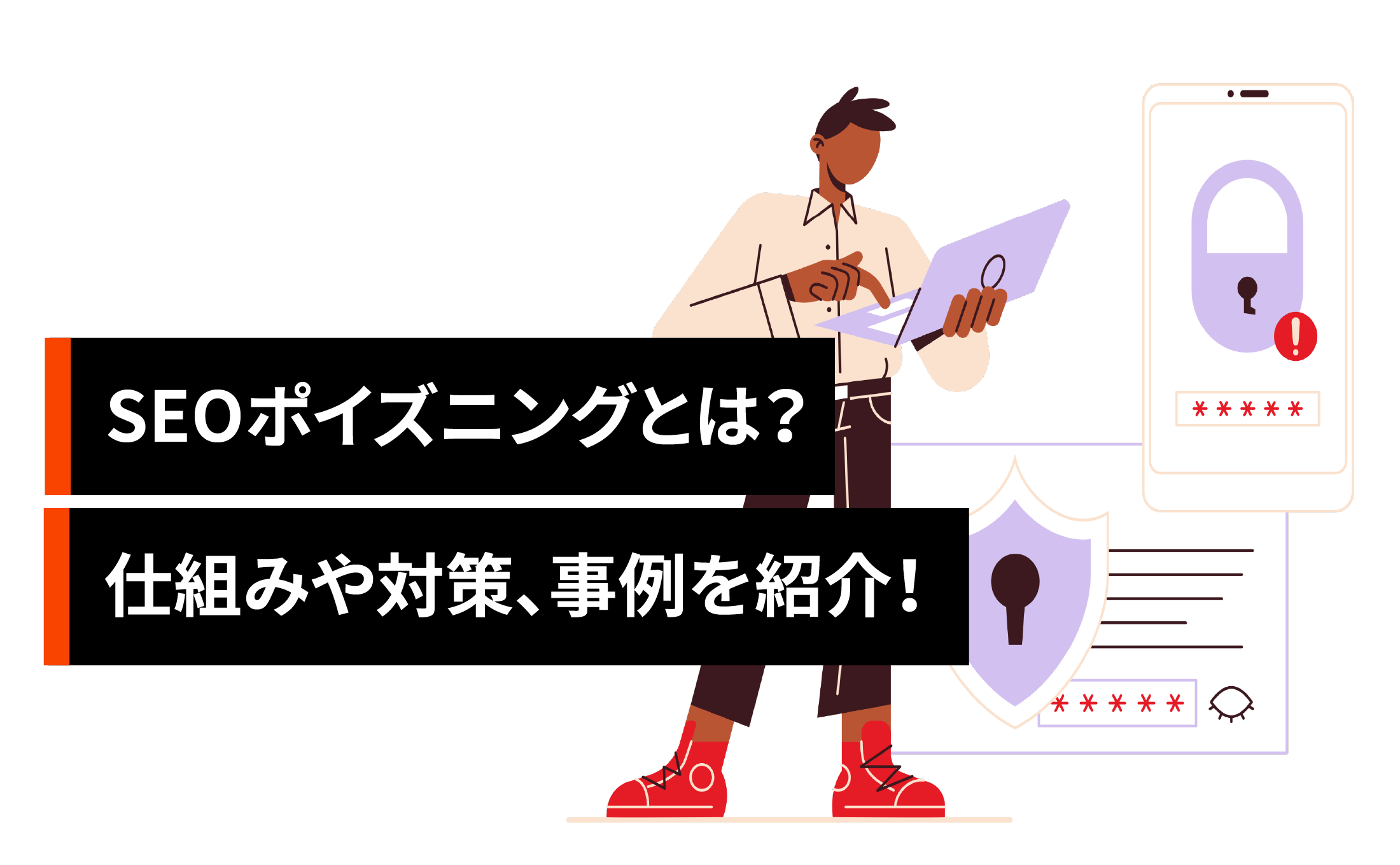
SEOポイズニングとは、検索エンジンの仕組みを利用して、不正なサイトを上位表示させ、サイトに流入したユーザーをマルウェアに感染させたり、詐欺サイトに誘導したりするサイバー攻撃を指します。
これは、攻撃者自身が新たに不正サイトを上位表示するケースだけでなく、すでに上位表示されているサイトに攻撃するケースも存在します。
そこで本記事では、SEOポイズニングの概要や対策方法について詳しく解説します。
本記事で解説する内容
① SEOポイズニングの概要
② SEOポイズニングされた詐欺サイトの特徴
③ SEOポイズニング対策(個人と企業)
本記事をお読みいただくことで、自社サイトのSEOパフォーマンスを高められますので、是非とも最後までお読みください。

X(旧: Twitter): @webkirin
COUNTER株式会社 代表取締役/SEOコンサルタント。
1993年生まれ。大学卒業後に外資系ITコンサルティング企業にてERP導入コンサルタントとして複数のシステム運用プロジェクトを経験。その後、CINCにてWebアナリスト、株式会社バンケッツにて不動産メディア事業責任者を経験し独立。フリーランスSEOコンサルタントを経験した後にニュートラルワークスにジョイン。SEO/コンテンツマーケティング戦略を得意分野とする。
◆ 経歴
2017年 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社/システムエンジニア(SAP Basis)
2018年 キャップジェミニ株式会社/ITコンサルタント(SAP SD/MM)
2019年 株式会社CINC/Webマーケティングアナリスト
2019年 株式会社バンケッツ/事業責任者(不動産メディア事業)
2020年 独立/Webマーケティングコンサルタント
2022年 株式会社ニュートラルワークス/執行役員 SEOコンサルティングリード
2024年 COUNTER株式会社 代表取締役
◆ 得意領域
・SEO戦略策定から実装支援(データベース・コンテンツ)
・コンテンツマーケティング戦略策定から実装支援
SEOポイズニングとは?

SEOポイズニングは、サイバー攻撃の一種であり、検索エンジンのアルゴリズムを悪用して不正なサイトを上位に表示させる手法です。
この攻撃の目的は、無防備なユーザーをマルウェアに感染させたり、詐欺サイトに誘導したりすることです。
具体的には、攻撃者は特定のキーワードやフレーズをターゲットにし、それに関連するコンテンツを持つ悪意のあるサイトを作成します。
SEOポイズニングの手口
SEOポイズニングは、攻撃者が巧妙に仕組まれた手口を用いて、ユーザーを不正なサイトへ誘導するサイバー攻撃の一種です。主に二つの手法が用いられます。
SEOポイズニングの手口
① 検索上位サイトから罠サイトにリダイレクトする
② ファイルレスマルウェアで訪問ユーザーを感染させる
ここでは、各手口について解説します。
検索上位サイトから罠サイトにリダイレクトする
SEOポイズニングの手口の一つとして、検索上位サイトから不正な罠サイトにリダイレクトする方法があります。
この手法は、攻撃者がSEOを悪用し、ユーザーを意図的に危険なサイトへ誘導(リダイレクト)するものです。
このリダイレクトは、通常、ユーザーが正規のサイトをクリックした際に発生します。例えば、検索結果の上位に表示されるサイトが、実際には攻撃者が仕掛けた罠である場合、ユーザーはそのサイトを訪れた瞬間に不正なページに転送されることになります。
このような罠サイトでは、マルウェアのダウンロードやフィッシング詐欺が行われることが多く、ユーザーの個人情報やデバイスの安全が脅かされる危険性があります。
ファイルレスマルウェアで訪問ユーザーを感染させる
ファイルレスマルウェアは、従来のマルウェアとは異なり、ユーザーのデバイスにファイルを直接保存することなく、システムのメモリ上で実行される悪意のあるコードです。
この手法は、検出を回避するために効果的であり、攻撃者にとっては魅力的な選択肢となっています。SEOポイズニングの文脈では、訪問者が不正なサイトにアクセスした際に、このファイルレスマルウェアが自動的に実行されることがあります。
具体的には、攻撃者は検索エンジンの結果に不正なリンクを挿入し、ユーザーがそのリンクをクリックすると、悪意のあるスクリプトが実行されます。
このスクリプトは、ユーザーのブラウザやオペレーティングシステムの脆弱性を利用して、ファイルをダウンロードすることなく、直接メモリ上で悪意のあるコードを実行します。
その結果、ユーザーの個人情報が盗まれたり、さらなるマルウェアがインストールされたりする危険性があります。
SEOポイズニングされた詐欺サイトの特徴
SEOポイズニングによって作成された詐欺サイトには、いくつかの共通した特徴があります。
SEOポイズニングされた詐欺サイトの特徴
① ポップアップの乱立
② デバイスのオーバーヒート
③ 文法間違いや誤字脱字が散見される
④ URLに不審な文字列が含まれている
ここでは、各特徴について解説します。
ポップアップの乱立
SEOポイズニングによって作成された詐欺サイトの特徴の一つが、ポップアップの乱立です。ユーザーの注意を引くために、さまざまなポップアップウィンドウが表示されます。
これらのポップアップは、通常の広告や通知とは異なり、ユーザーに対して緊急性を訴えかける内容が多く、例えば「ウイルスが検出されました」や「特別なオファーがあります」といったメッセージが表示されることが一般的です。
ポップアップが乱立することで、ユーザーは混乱し、誤ってクリックしてしまう可能性が高まります。
特に、ポップアップが閉じられない場合や、閉じるボタンがわかりにくい位置に配置されている場合、ユーザーは意図せずに不正なリンクをクリックしてしまうことがあります。
このような行動が、マルウェアのダウンロードや詐欺サイトへの誘導につながるのです。
デバイスのオーバーヒート
SEOポイズニングによって誘導される詐欺サイトの一つの特徴として、デバイスのオーバーヒートが挙げられます。悪意のあるサイトがユーザーのデバイスに過剰な負荷をかけることによって引き起こされる現象です。
具体的には、詐欺サイトが大量の広告やスクリプトを読み込むことで、CPUやメモリの使用率が急激に上昇し、結果としてデバイスが熱を持つことになります。
オーバーヒートは、デバイスのパフォーマンスを低下させるだけでなく、ハードウェアに深刻なダメージを与える可能性もあります。
特に、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスでは、熱による影響が顕著に現れることがあります。
ユーザーが詐欺サイトにアクセスした際に、デバイスが異常に熱くなる場合は、そのサイトが危険である可能性が高いと考えられます。
文法間違いや誤字脱字が散見される
SEOポイズニングによって作成された詐欺サイトの特徴の一つに、文法的な間違いや誤字脱字が多く見られることがあります。
これらのサイトは、通常のウェブサイトとは異なり、急いで作成されたり、質の低いコンテンツが使用されたりするため、文章の整合性が欠けていることが多いのです。例えば、明らかに不自然な日本語や、意味が通じないフレーズが散見されることがあります。
このような文法的なミスは、訪問者に対して不信感を与える要因となります。通常、信頼性の高いサイトでは、コンテンツの質が重視され、校正や編集が行われるため、誤字脱字はほとんど見られません。
しかし、SEOポイズニングによる詐欺サイトは、短期間で多くのユーザーを騙すことを目的としているため、こうした基本的なチェックが行われていないのです。
URLに不審な文字列が含まれている
SEOポイズニングの詐欺サイトには、しばしば不審な文字列が含まれたURLが見受けられます。これらのURLは、通常のウェブサイトとは異なる構造を持っており、ユーザーを混乱させることを目的としています。
例えば、正規のサイト名に似せた文字列や、意味不明な数字や記号が組み合わさったものが多く見られます。このようなURLは、攻撃者がユーザーを騙して不正なサイトに誘導するための手段として利用されます。
ユーザーが無意識のうちにクリックしてしまうことで、マルウェアに感染したり、個人情報を盗まれたりする危険性が高まります。特に、URLが短縮されている場合や、HTTPSではなくHTTPで始まる場合は、注意が必要です。
SEOポイズニングの被害事例
SEOポイズニングの被害事例として代表的なものが下記の2つの事例となります。
SEOポイズニングの被害事例
① 「えきねっと」のフィッシングサイトへの誘導
② 検索結果の異常な変動
ここでは、各事例について紹介します。
「えきねっと」のフィッシングサイトへの誘導
SEOポイズニングの被害事例として特に注目されるのが、JR東日本が運営する「えきねっと」のフィッシングサイトへの誘導です。
この事例では、攻撃者が検索エンジンの結果を悪用し、正規の「えきねっと」サイトに似た偽サイトを上位に表示させました。
ユーザーが「えきねっと」と検索すると、見た目が非常に似ている詐欺サイトが表示され、
unsuspecting users were tricked into entering their personal information, such as credit card details and login credentials.
このようなフィッシングサイトは、正規のサイトとほぼ同じデザインを持っているため、ユーザーは容易に騙されてしまいます。
特に、急いでいるユーザーや、オンラインでの予約を初めて行う人々は、注意を怠りがちです。結果として、個人情報が盗まれたり、金銭的な被害を受けたりする危険性が高まります。
検索結果の異常な変動
SEOポイズニングの被害事例の一つとして、検索結果の異常な変動が挙げられます。
これは、攻撃者が不正な手法を用いて、特定のキーワードに関連する検索結果を操作し、ユーザーを詐欺サイトやマルウェアを含むサイトへ誘導することを目的としています。
具体的には、攻撃者は特定のキーワードに対して不正なコンテンツを作成し、それを検索エンジンの上位に表示させることで、ユーザーがそのサイトをクリックするよう仕向けます。
結果として、検索結果が通常とは異なるサイトで埋め尽くされ、正規の情報を探しているユーザーが不正なサイトに誘導されるという事態が発生します。
個人でやるべきSEOポイズニング対策
SEOポイズニングから身を守るためには、個人が日常的に実践できる次のような対策があります。
個人でやるべきSEOポイズニング対策
① 意図しないサイトが表示されら速やかに離脱する
② 日常的に閲覧するサイトはブックマークする
③ OSを常に最新の状態にしておく
ここでは、各対策について解説します。
意図しないサイトが表示されら速やかに離脱する
SEOポイズニングのリスクを軽減するためには、意図しないサイトが表示された際に迅速に離脱することが重要です。
特に、検索結果から不審なリンクをクリックしてしまった場合、マルウェアや詐欺サイトに誘導される危険性が高まります。
ユーザーは、表示されたサイトが信頼できるものであるかどうかを常に意識し、少しでも怪しいと感じたらすぐにブラウザを閉じるか、他のサイトに移動することが推奨されます。
日常的に閲覧するサイトはブックマークする
SEOポイズニングのリスクを軽減するためには、日常的に利用するサイトをブックマークすることが効果的です。
ブックマークを活用することで、信頼できるサイトへのアクセスを簡単に行うことができ、検索エンジンを介さずに直接訪問することが可能になります。
特に、金融機関やショッピングサイト、重要な情報を提供するサイトなど、頻繁に利用するサイトは必ずブックマークしておくべきです。
OSを常に最新の状態にしておく
基本的なセキュリティ対策を講じることが重要です。その中でも、オペレーティングシステム(OS)を常に最新の状態に保つことは、効果的な手段の一つです。
OSのアップデートには、セキュリティパッチやバグ修正が含まれており、これらを適用することで新たに発見された脆弱性からシステムを守ることができます。
企業・組織がおこなうべきSEOポイズニング対策
企業や組織がSEOポイズニングの被害を未然に防ぐためには、次にあげるいくつかの具体的な対策を講じることが重要です。
企業・組織がおこなうべきSEOポイズニング対策
① 認証強化
② Web改ざん検知ツールの導入
③ 従業員へのセキュリティ教育
④ アンチウイルスやEDRを導入
ここでは、各対策について解説します。
認証強化
SEOポイズニングの対策として、認証強化は重要なステップです。
特に、企業や組織が運営するウェブサイトでは、ユーザー情報やデータを守るために、強固な認証システムを導入することが求められます。
まず、パスワードの強化が基本です。ユーザーには、英数字や記号を組み合わせた複雑なパスワードを設定するよう促し、定期的な変更を推奨します。
また、二段階認証(2FA)を導入することで、万が一パスワードが漏洩した場合でも、追加の認証手段があるため、セキュリティを一層強化できます。
さらに、ユーザーアカウントの管理も重要です。不要なアカウントは速やかに削除し、アクセス権限を適切に設定することで、内部からの脅威を防ぐことができます。
Web改ざん検知ツールの導入
SEOポイズニングのリスクを軽減するためには、Web改ざん検知ツールの導入が非常に重要です。
これらのツールは、ウェブサイトのコンテンツや構成に対する不正な変更をリアルタイムで監視し、異常を検知する機能を持っています。
導入する際には、まず自社のニーズに合ったツールを選定することが重要です。多くのツールが市場に出回っており、機能や価格帯もさまざまです。
例えば、変更履歴のトラッキング機能や、異常を検知した際のアラート機能が充実しているものを選ぶと良いでしょう。また、定期的なレポート機能があると、サイトのセキュリティ状況を把握しやすくなります。
従業員へのセキュリティ教育
企業や組織において、従業員へのセキュリティ教育も重要です。
教育プログラムを通じて、従業員がどのようなリスクにさらされているのかを理解し、適切な対策を講じることが求められます。
まず、従業員にはフィッシングメールや不審なリンクの見分け方を教えることが重要です。これにより、攻撃者が仕掛ける罠に引っかかるリスクを減少させることができます。
また、定期的にセキュリティに関するワークショップやトレーニングを実施し、最新の脅威や対策についての情報を提供することも効果的です。
アンチウイルスやEDRを導入
SEOポイズニングに対抗するためには、アンチウイルスソフトウェアやEDR(Endpoint Detection and Response)の導入が不可欠です。
これらのツールは、マルウェアや不正アクセスをリアルタイムで検知し、迅速に対応する能力を持っています。
特に、EDRはエンドポイントの監視を強化し、異常な挙動を早期に発見することができるため、企業のセキュリティ対策において欠かせない存在となっています。
アンチウイルスソフトウェアは、既知のウイルスやマルウェアを検出するだけでなく、定期的なアップデートを通じて新たな脅威にも対応します。
自社サイトがSEOポイズニングの被害にあった場合の対処法
自社サイトがSEOポイズニングの被害に遭った場合、次にあげるような迅速かつ適切な対処が求められます。
自社サイトがSEOポイズニングの被害にあった場合の対処法
① 感染したWebサイトの特定と隔離
② 専門家に相談しマルウェアや不正なコードの除去
③ バックアップからのWebサイトの復旧
ここでは、各対処法について解説します。
感染したWebサイトの特定と隔離
SEOポイズニングの被害に遭った場合、まず最初に行うべきは感染したWebサイトの特定です。これには、サイトのトラフィックやパフォーマンスの異常を監視することが重要です。
例えば、突然のアクセス数の減少や、特定のページへの異常なトラフィックの増加が見られた場合、何らかの問題が発生している可能性があります。また、ユーザーからの報告やフィードバックも重要な手がかりとなります。
感染が疑われる場合は、速やかにそのWebサイトを隔離する必要があります。隔離とは、感染したサイトを一時的にオフラインにすることを指します。これにより、さらなる感染拡大やユーザーへの被害を防ぐことができます。
専門家に相談しマルウェアや不正なコードの除去
自社サイトがSEOポイズニングの被害に遭った場合、迅速かつ適切な対応が求められます。
その中でも特に重要なのが、専門家への相談です。マルウェアや不正なコードの除去は、専門的な知識と技術が必要な作業であり、素人が手を出すと逆に状況を悪化させる可能性があります。
まず、信頼できるセキュリティ専門家や企業に相談することが重要です。彼らは、感染したWebサイトの特定や、どのようなマルウェアが存在するのかを詳細に分析し、適切な除去手順を提案してくれます。
さらに、マルウェアや不正なコードを除去するだけでなく、再発防止策についてもアドバイスを受けることができます。これにより、同様の攻撃を未然に防ぐためのセキュリティ強化策を講じることができ、自社サイトの安全性を高めることが可能です。
バックアップからのWebサイトの復旧
SEOポイズニングの被害に遭った場合、最も重要なステップの一つがバックアップからのWebサイトの復旧です。
定期的にバックアップを取っている場合、感染したWebサイトを迅速に元の状態に戻すことが可能です。バックアップは、サーバー上のデータやファイルを安全に保存するための手段であり、万が一の事態に備えるために欠かせません。
復旧作業を行う際には、まず感染したWebサイトの特定と隔離を行い、その後、バックアップデータを使用してサイトを復元します。このプロセスでは、最新のバックアップを選択することが重要です。
古いバックアップを使用すると、再度感染するリスクが高まるため、常に最新の状態を保つことが求められます。
まとめ
本記事では、SEOポイズニングの仕組みや手口、被害事例、そして対策方法について詳しく解説しました。
特に、個人や企業が取るべき対策は重要です。個人は、意図しないサイトから速やかに離脱することや、日常的に利用するサイトをブックマークすることでリスクを軽減できます。
一方、企業は認証強化やWeb改ざん検知ツールの導入、従業員へのセキュリティ教育を通じて、組織全体の防御力を高める必要があります。
SEOポイズニングの脅威は常に進化しているため、最新の情報を把握し、適切な対策を講じることが求められます。自社サイトが被害に遭った場合には、迅速に専門家に相談し、適切な対応を行うことが重要です。
これらの対策を通じて、安心してインターネットを利用できる環境を整えていきましょう。